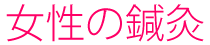
東洋医学でみる病の原因は、大きく次の3つに分けられます。
①自然現象から受けるもの → 外因(外邪・六気・六淫)
②感情 → 内因(七情)
③生活習慣 → 不内外因
生活習慣による病の原因のことを東洋医学では「不内外因(ふないがいいん)」と言います。
これはいたって当たり前のことで、以下のようなことです。
・飲食物の量の過不足:食べ過ぎ・栄養不足
・飲食物の偏り:偏食
・労働のしすぎ
・休養の不足
・房事の不摂生
・外傷
房事とは、性交のこと。
房事の不摂生は、腎のエネルギーを消耗します。
また、房事を度を越して行ったり、酔ってやったり、房事の後に風にあたったりすると、
病気を引き起こすと言われています。
五労の労は労働の労。
労働のしすぎ、運動のしすぎは臓腑の機能を損なうということ。
それが五臓:肝心脾肺腎に分類されます。
・肝:久行
歩き過ぎ、動き過ぎると、肝の働きが悪くなります。
肝は筋肉をつかさどっているので、歩き過ぎたり、動き過ぎれば、
筋肉が疲労します。
・心:久視
目の使い過ぎは、心の働きが悪くなります。
目は肝とも深く関係しています。
・脾:久坐
長時間座りっぱなしは、脾の働きが悪くなります。
デスクワークの長い人は足のむくみや腰痛だけでなく、胃腸の働きにも注意しましょう。
・肺:久臥
横になってばかり(特に病で)は、肺の働きが悪くなります。
長期に渡り病で臥っていて、もともとの病気ではなく、
肺を患って亡くなるという話、よく耳にします。
・腎:久立
長時間立ちっぱなしは、腎の働きが悪くなります。
ずっと立っていると、エネルギーを消耗し、腰は疲れます。
腰痛と腎は深い関係にあります。
また腎が弱い方は、長い時間立っていることができず、
体を横にしたがります。
copyright 一般社団法人女性の鍼灸 womens-acupuncture